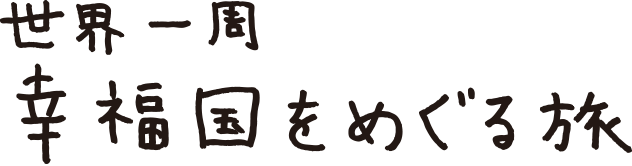ニュージーランドの教育は、
想像通り、自由でのびのび。
ベースはヨーロッパ教育で「個性を伸ばす」もの。
ここも移民でなりたつ国家であり、
多様性がものすごく、
個人個人が主張しないと置いていかれるから。
驚いたのは、学校選びは自分の進路に合わせてするため、
転校は普通であること。
校長先生や、担任の先生によっても教育方針が大きくと変わるから、
合わないと思ったら、即転校する。
中国人は、とくにすごいみたい。
また、親子の会話の内容は日本とは違い、
「将来からの逆算」。
「将来は決めた?それなら、この学校がいいね」
「これになりたいから、この勉強したい」
「 仕事決めたら、いつでも学校辞めていいよ」
「まだ決まらないから、とりあえず大学いく」
日本とは違い、将来の仕事にダイレクト。
大学は入学しやすく、卒業は難しい。

また、欧米文化と同様、親は褒め上手。
小学生の年齢では、教科書はなく授業は先生次第。
暗記は必要ないという発想。
なぜなら、調べればわかるから。
一つの事象から、どう考えるか、
どうしてそれをするかの意味が重要。
教育に家庭の協力が重要。
送り迎えやボランティアなど親の参加負担は大きいが、
コミュニケーションは増える。
寄付概念も大きく、親たちのドネーションで
成り立つ部分も多い。
ダイバーシティも学ぶ。
発達障害も国籍も、子供達は気にしていない。
LGBTは、中学からカミングアウトしはじめたり。

ただ、大学からは大人になり、
自分で責任をもって生きるべく親に外に出される。
そのプレッシャーに押しつぶされる子もいて、
それは大きな課題にもなっている。
もちろん、ギャップイヤーで
将来を考える時間をもつことができたり、
大人になってからの学び直しなど、
ヨーロッパ教育のよさはしっかりあるのだが。
この国の教育は自由。
でも、それにも増すほど社会は自由だからこそ、
そこを生き抜くための自主性や力を育てることが必須なのだ。
しかし、この大自然の中での学びはうらやましい。
今後、世界に本当に必要な人材をを育てていく気がする。
※参考世界ランキング
・未来教育指数1位
・教育に対する支出1位
・ニュージーの大学は3校とも世界大学ランキング上位3%入り。
(ニュージーランド 1・2・4・5・6 )